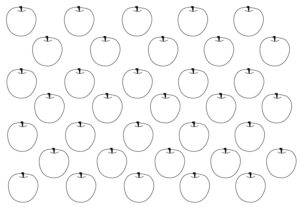「特別でありたい」「一番でありたい」
これは、まさに、「自我」の主張。
「自分が一番世界で一番かわいそう」とか「自分は例外です」というのも、「特別でありたい」「一番でありたい」というのも同じ。
********
自我は、人類すべて、というか、この世に生まれた時点で仕掛けられたもので、たとえば「特別でありたい」とか「選ばれしものでいたい(かもしれない)」という声が「自分の声」と感じる場合は、自我に同一化しているということで、自我は”本来の自分自身”ではない。
「特別でありたい」とか「選ばれしものでいたい(かもしれない)」とか、この声は、まず、自我として、受け入れること。動かさないこと。これだけが、「できること」。
どんな自分の声にも耳を澄ませ、外側をすべて「わたし」としてただみて、自我であろうが、インナーチャイルドであろうが、すべてを「そのまま、みる、動かさない、なんとかしようとしない、ただ、みる」これも、そのままで、いいのよ、なのです。
感情も、感覚も、なにもかも、とにかく、そのままを、認めて、受け入れる。問題視しない、分析しない、ジャッジしない、コントロールしようとしない。
これも、そのままでいいよ、です。
唯一、わたしがわたしのために、できること。自愛の話。
********
自我は自我なのではない、人類、この世界、この夢の世界の仕掛け。これを頭で理解しようとしても、遠回りするだけ。遠回りしたとしても、誰も裁かない。ただ、唯一の存在は、見守ってくださっている。
********
「特別でありたい」とか「選ばれしものでいたい(かもしれない)」とか、これを、隠し持ったまま、生きていると、だれかと「自我の人生(つまり悪夢)」を共有することを無意識的に望むようになることは、よくあること。
自我は、無意識でそれを望み、悪夢を一緒に見てくれそうな人を「この人ぞ」と選ぶ。
自我は、たとえば、家族だったり、恋人だったり、好きな人だったり、お友達だったり、憧れの人だったり、自分によくしてくれた人だったり、そういった、「大事な人」を、必ず、傷つける。
それを予期して、人を遠ざけたとしても、何かで苦しめている。
********
これの「墨状態(薄い墨ではなく濃い墨)」は、心理学では、共依存(関係嗜癖)と、呼ばれている。(対象が人間でない場合は、嗜癖)
そして、嗜癖・共依存の自助グループのような場所でも、「祈り」がされていた。
自我信仰が強い場合は、信仰先を自我から「自我以外」に変えれば良いだけ。
もともと信仰力は強いので、その信仰先を「自我」から「自我以外」に変えたら、すごいことになる。このすごさ、これはもう、筆舌に尽くし難い。
********
「特別でありたい」とか「選ばれしものでいたい(かもしれない)」とか「こうでありたい」という自我信仰力が強かったかもしれない、と、気づきはじめたころ、つらくなったり、虚無感空虚感鬱、なにもできなくなる、などなどが、現れることは、よくあること。
祈りつづけている場合は、「ひとりになる」「暇になる」「あまりに平々凡々すぎる」のような状況になることも、よくあるようです。これは、幸運なことなのだけれども、
自我はこれを不安だと解釈させたり、また問題を見つけようとさせたり、あの手この手を、使って自我を信仰するように、そそのかしてきます。あるときは静かに、あるときは強烈に。あるときは悪魔のようにして、あるときは神様のようにして。
ここでまた、自我は「なんとかしなければならない」「どうにかしなければならない」と囁くかもしれないし、感情やエネルギーのほうで、なんらかが現れるかもしれない(厳密にはすべてなにもかもが幻想、不変以外は幻想)。
自我を信じ込んでいると、「なにもできない状態・環境・出来事」、つまり、試練、八方塞がりの状態となる。
あがけばあがくほど、八方塞がり感は強くなり、苦しみは増幅する、自我の思う壺というか、自我的鏡の法則状態。
こういうとき、どうすればよいかを、ほんとうはもう、知っている。ずっと、包まれている。
外に探せば探すほど、「かたちあるもの」に求めれば求めるほど、抵抗すればするほど、
自我(自動的に生じる自分だといいはる思考、感情など)はぶくぶくと太り、「ますます脅威感」を持つ(※すべてただの悪夢)
神様は、片時も離れたことがない。
裁くことをしらない、罪を観測できない、愛しかしらない、ただそれでしかない神は、心の奥で、いつものように、包みこんでいる。