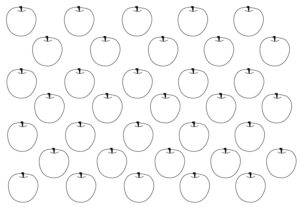内側にぐんと潜っていく力があるとき。
けれども、同時に、エゴと同一化したままだ(自分や他者を責めたり、ジャッジしたり、禁止したり、コントロールしたりしやすい)という場合。
「エゴは、自分ひとりだけのものじゃない」
ということを、すっかり忘れてしまう、ということがあります。
これは、言い方を変えると、
「エゴ特有の、”個人という私ひとりだけが感”、に直面する」
ということでもあります。
この”個人という私ひとりだけが感”というのは、
さみしさ、孤独感、疎外感、取り残されるような感じ、特別を求める気持ち、優越感、万能感、罪悪感、恥・・・いろんなものに流れています。
けれども、この”個人という私ひとり”という感じ、というのが、エゴのシステムゆえに浮かんできているものです。
真の個性や、真の多様性というのは、たったひとつの内なる源から現われ出るものなのですが、
エゴは、個性や多様性を、「真似」「コピー」とすり替えようとします。
そして、内なる源からの表現をしたいのに、できない、という状態において、私たちは、苦しみや罪悪感や欠乏感や不足感などを感じることがあります。
それで、自分の中に浮かんでくる「おそらくこれはエゴだろう」というものを、
「自分だけが、これを考えている」と、無意識的に捉えていると、
とてもとても、苦しく、恐ろしい思いをすることになります。
とてもとても、苦しくて、恐ろしいとき、私たちは、それを、感じないようにすることがあります。
けれども、その苦しみ、というのは、自分ひとりだけのものじゃない、ということ。
これは「みんなも苦しんでいる」と認識しようということではなくて(これだと、苦しみを自分も誰かも保持し続ける必要が出てくる)
「エゴの思考ルート」みたいなものがあって、一人ひとりがそれにアクセスするかしないかの自由があって、それを選択する力は全員にある、ということ。
苦しみじゃない、もう一つの選択肢を、
みたい、わかりたい、知りたい、だから、体験したい、
という気持ちが、自分の中にあることに、素直になってあげること。
自分なんかには、そんなのは無理だというのは、春になって、お日様に向かって、ぱぁっと、お花を咲かせようと、すくすくと育っている芽を、片っ端から摘もうとするようなもの。
実際には、その芽は決して絶たれることはないのですが、エゴはそれを「疲れた」「なんで私ばっかり」と認識することがある、ということ。
「自分はそんなにたくさんのものはいらない。そこそこでいい。ほどほどでいい。そんな奇跡なんて大袈裟なもの望まない」というのは、フカフカの土の中で眠っている種に対して、「枯れた、貧相な状態で芽を出してほしい」と思うようなもの。
「枯れた、貧相な状態で芽を出してほしい」と思うことが、謙虚さであると、エゴは信じている。
金木犀が黄金色に咲き、甘く上品な香りを漂わせ、秋の訪れを優雅に歌い、人々から愛られることを、エゴは「そんな金木犀は、贅沢で、欲深く、恥ずかしく、みっともなく、悪いことだ」と解釈をする。
だからと言って、エゴが邪悪だというわけではない。ただ、あり得ないだけである。
「金木犀が、贅沢で、欲深く、恥ずかしく、みっともなく、悪い」なんてことは、ただ、あり得ないだけであって、その解釈について深刻に捉える必要もなく「何言ってんだか(笑)」という話なだけである。
けれども、エゴはここでもまた「病気なんじゃないか」と、問題視や深刻視をしようとする。
投影、というのも、ほんとうは、自分ひとりだけの、個人的なものじゃないということ、自分ひとりだけの個人的なものにしようとするためのもの。